 模範解答例
模範解答例 【公務員試験】論文頻出テーマの模範解答例を一挙公開!
「公務員試験」で出題される論文頻出テーマについて、「王道の模範解答例」を公開します!
 模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  模範解答例
模範解答例  コラム
コラム 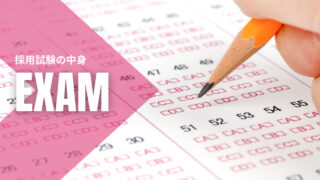 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム 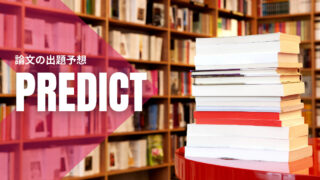 コラム
コラム  コラム
コラム  コラム
コラム