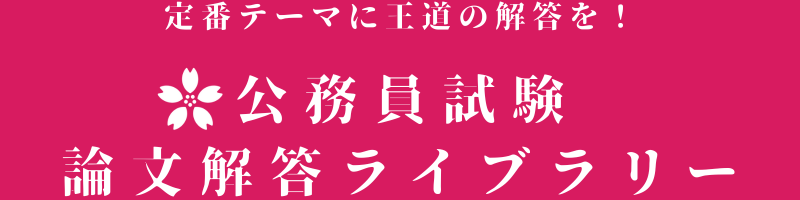こんにちは!
「定番テーマに王道の解答を! 公務員試験 論文解答ライブラリー」の編集長です。
このブログは、公務員採用試験の論文試験でよく出題されるテーマや、試験種ごとの論文試験の過去問について、模範解答例を紹介しています。
模範解答例を書いた人

旧帝大を卒業後、国家公務員として省庁で人事の仕事をしていました。
現在は退職し、公務員志望者の論文添削や面接指導などをおこなっています。
この記事では、消防官採用試験の論文試験で頻出テーマの模範解答例を紹介します。
論文テーマはこちら。
模範解答例は、論文指導のプロが予備校の論文構成に準じて答案を書き、推敲を重ねた良質な答案です。
この模範解答例を読めば、答案を書くために必要な知識を効率的にインプットすることができます。
また、模範解答例をお手本にしながら自分で答案を書いてみることで、万全な論文対策が可能です。
これから受験を控える皆さんに、ぜひ活用してもらえると嬉しいです。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「①安全・安心な社会」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
安全・安心な社会を実現するため、消防はどのような取り組みを行う必要があるか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
安全・安心な社会とは、住民が日常生活で災害の不安を感じることがなく、仮に災害の被害にあった場合でも早期に解決が図られ、身体的・精神的な苦痛から解放される社会である。
②重大性
近年、災害は激甚化・頻発化している。
実際、平成 28 年の熊本地震以降、多数の死傷者が生じる大規模災害が毎年のように発生している。
こうした状況では、住民が安全・安心に暮らすことは難しい。
したがって、安全・安全な社会の実現に向けて、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、平時から地域に密着した備えを図るべきである。
災害はいつ・どこで発生するか分からない。
有事の際に迅速な対応ができるよう、万全に準備しておく必要がある。
まず、平素から管内の危険箇所に関する実態把握に努めるとともに、ドライスーツや投光器などの装備資機材を十分に整備しておくことが重要である。
加えて、自治会や消防団と連携した避難訓練の実施を強化する。
このとき、消火器やタンカーを用いた実践的な訓練内容をコーディネートするほか、多様な住民の参加を呼び掛ける役割が消防には求められる。
ただし、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な住民など、避難訓練への参加が困難な住民に対しては、可能な限り戸別訪問を実施し、避難方法の相談に乗るなどの配慮が必要であろう。
こうした取り組みにより、住民に「消防から守られている」という安心を提供することが大切だ。
第二に、災害時の救出救助能力の向上を図るべきである。
災害による建物の倒壊・河川の氾濫・住宅の浸水・土石流の発生に住民が巻き込まれた場合、一刻も早い救出救助が必要となる。
まず、災害訓練の充実を図ることだ。
訓練に際しては、家屋の倒壊や土砂災害を再現した現場からの救出救助、夜間における救出救助など、過去の災害の教訓を踏まえた訓練を実施することが望ましい。
同時に、訓練では消防官同士のチームワークを大事にしたい。
仲間同士で切磋琢磨するとともに、先輩から熟練した指導を受けることで、救出救助能力を高め合う。
訓練でできないことは、実際の現場ではできない。
消防は、住民の命を災害から守る気概を持ち、厳しい訓練に臨む必要がある。
加えて、災害時には要救助者の心に寄り添う対応が大切だ。
倒壊した家屋の下にいるだろう要救助者を、たとえ返答がなくても励まし続けることが、ときに命を救うことにつながる。
④まとめ
私は消防官となり、日頃の訓練や地域での活動に全力で取り組み、安全・安心な社会の実現に貢献したい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「②火災」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
火災の被害から住民を守るため、消防はどのような取り組みを行うべきか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
近年、火災発生件数は全国的に減少傾向にある。
しかし、火災による死者数の大部分が住宅での火災によるものであり、その死者数は年間約1,000人に上る。
②重大性
住宅火災の重大性はなにか。
それは、高齢者や障害者などの社会的弱者が犠牲になりやすいことである。
実際、火災による死者数のうち、約7割を高齢者が占める。
ひとたび出火すると炎は瞬く間に広がり、気付いたときには火煙が周り逃げ遅れてしまうのが火災の怖さだ。
したがって、火災の被害から住民を守るため、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、住宅火災の出火原因が、主に失火によるものであることだ。
たとえば、「たばこの火の不始末」「コンロの消し忘れ」が挙げられる。
第二に、火災発生時に初期消火が行われない場合が多いことだ。
④解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、火災予防に関する啓発活動を強化するべきである。
失火による住宅火災を防ぐには、「寝たばこは絶対にしない」「コンロを使うときは火のそばを離れない」「ストーブの周りに燃えやすいものを置かない」などの生活習慣が重要となる。
したがって、消防は、生活の中で出火につながる危険のある行動について理解を促し、予防策を周知するよう努める必要がある。
こうした情報を分かりやすく示したリーフレットを作成し、高齢者やその家族、高齢者がよく利用する施設に配布するなど、取り組みを積極的に行っていくべきである。
とりわけ、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な住民に対しては、可能な限り戸別訪問を実施して周知するなど、住民それぞれの安全安心を確保するためにきめ細やかな対応が求められるだろう。
第二に、火災発生時に初期消火が行われるよう、対策の普及促進を図るべきである。
まず、火災を小さなうちに消して安全に避難するため、消火器の用意と使いかたの確認が欠かせない。
加えて、火災の早期発見には住宅用火災警報器を設置し、定期的な点検や交換を行うことが有用である。
したがって、消防は、こうした初期消火への備えを促すほか、部屋を整理整頓し、避難経路や避難方法を常に確保しておくよう周知する必要がある。
ただし、高齢者や身体の不自由な住民は、こうした対策をひとりで行うことが難しい。
そこで、自治会や消防団と連携し、地域ぐるみの防火対策を推進することが望まれる。
たとえば、地域で防火防災訓練を実施し、高齢者が消火活動を実際に体験したり、身体の不自由な住民の家庭を訪問し、避難方法の相談に乗ったりする取り組みを積極的に行っていくべきである。
⑤まとめ
私は消防官となり、火災による被害から住民を守るため、地域に密着した防災活動に励みたい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「③救急」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
救急需要の増大に対して、消防はどのような取り組みを行うべきか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
近年、救急自動車による救急出動は全国的に増加傾向にある。
なお、令和3年中の搬送人員のうち、半数以上を高齢者が占める。
一方、搬送人員のうち半数近くが、緊急性の乏しい軽症者であった。
②重大性
救急需要の増大は、どのような影響をもたらすか。
それは、救急自動車の現場到着が遅れ、救命率が低下する懸念があることだ。
実際、現場到着所要時間は近年延伸している。
したがって、救急需要の増大に対応するため、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、高齢化の進展により、救急需要のさらなる増大が見込まれることだ。
第二に、緊急性の低い救急要請が増加していることだ。
たとえば、救急自動車を呼んだ理由として、「夜間や休日で診療時間外だった」「軽症・重症の判断がつかなかった」が一定程度を占めている。
④解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、高齢者の怪我や急病、応急処置に関する啓発活動を強化するべきである。
高齢者は、家の中で転倒して骨折し、動けなくなる事故が少なくない。
また、猛暑でも冷房をつけずに熱中症になり重症化することや、真冬に熱い風呂に入り意識を失うこともある。
こうしたケースは、あらかじめ知識があれば一定程度防ぐことが可能だ。
したがって、消防は、家の中で起こりうる事故についての理解を促し、事故の予防策や応急処置の方法を周知することが重要である。
具体的には、住民が気軽に参加できる講習会やイベントを開催すること、日常的に起こりうる怪我や病気に関するパンフレットの作成に力を入れることが挙げられる。
それにより、高齢者の急病や怪我の重篤化を防ぐとともに、救急出動件数の抑制につながると期待される。
第二に、救急自動車の適正利用に関する啓発活動を強化するべきである。
救急自動車の適時・適正な利用を支援するサービスとして、救急相談センター「#7119」(実施している自治体のみ)や救急受診アプリ「Q助」がある。
こうしたサービスを身近で安心して利用できる救急の相談窓口として認知してもらうためには、医療機関の案内や医師・看護師等による救急相談が受けられることなど、サービスの内容を具体的に伝えていくことが大切である。
とりわけ、乳幼児のいる家庭や一人暮らしの高齢者に対しては、サービスを分かりやすく伝えるパンフレットや、電話の近くに貼るステッカーを配布するなどの取り組みを積極的に行っていくべきであろう。
⑤まとめ
私は消防官となり、救急に関する高度な技術や知識を身に付け、それを住民に分かりやすく伝えることで、救急行政に貢献する所存である。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「④地震」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
地震の被害から住民を守るため、消防はどのような取り組みを行う必要があるか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
東日本大震災の被害は記憶に新しい。
近い将来、首都直下地震や南海トラフ巨大地震など、大規模地震の発生が全国で予想されている。
②重大性
大規模地震の重大性はなにか。
一つに、多数の死者が見込まれることだ。
建物の倒壊や火災による脅威が、とりわけ高齢者や身体の不自由な住民を襲う。
したがって、地震の被害から住民を守るため、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、建物の耐震化・出火防止対策が不十分なことだ。
築年数の古い木造住宅を中心に、耐震基準に満たない住宅が依然として多いほか、火災の多発と延焼が懸念される。
第二に、地域防災力の低下が懸念されることだ。
少子高齢化や核家族化の進展により、地域の助け合いが希薄化している。
④解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、建物の耐震化・出火防止対策を強化し、建物の倒壊や火災による被害の軽減を図るべきである。
耐震化の推進については、国や地方自治体において耐震改修助成などの事業が実施されている。
出火防止対策については、感震ブレーカー・火災報知器・消火器の設置が欠かせない。
したがって、消防はこうした施策を住民に広く広報啓発する必要がある。
情報発信においては工夫をしたい。
ホームページや広報誌のみならず、SNSなど多様な手法で発信するほか、子ども連れで気軽に参加しやすい防災イベントの開催など、取り組みを積極的に行うことが重要である。
第二に、地域防災力の向上を図り、地域による助け合いを強固にするべきである。
建物の耐震化・出火防止対策は有効であるが、どれだけ対策を講じたとしても、被害を完全に防ぐことは困難だ。
そこで重要となるのが、住民同士で助け合う地域の防災力である。
実際、阪神・淡路大震災では、倒壊した家屋から救出された人のうち7割以上が、家族や近隣住民の手によるものであった。
したがって、消防は、住民や消防団が救助活動や初期消火活動を安全に担えるよう、救助備品や消火設備の確保を支援することが求められる。
加えて、タンカーや消火器を用いた実践的な防災訓練をコーディネートし、多様な住民の参加を呼び掛けることも、消防の重要な役割といえよう。
⑤まとめ
私は消防官となり、未曽有の大地震の教訓を忘れず、平時から住民の命を守るための活動に貢献したい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「⑤テロ事件」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
テロ事件の脅威に対応するため、消防はどのような取り組みを行う必要があるか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
近年、過激派組織らによるテロ事件が、世界各地で頻発している。
我が国も例外ではない。
なぜなら、一部の過激派組織が我が国や邦人をテロの標的として、繰り返し名指ししているからだ。
②重大性
テロ事件の重大性はなにか。
それは、ひとたび発生すれば不特定多数の住民が死傷する危険があることだ。
したがって、テロ事件に適切に対処するため、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、大規模集客施設や公共交通機関がテロの標的になりやすいことだ。
実際、欧米諸国のショッピングモールや地下鉄で、大勢の一般人が犠牲になるテロ事件が発生している。
第二に、テロ事件が多様化・複雑化していることだ。
組織的なテロリスト集団のみならず、テロ組織のプロパガンダの影響を受けて過激化した個人によるテロ事件の発生が、世界各地で増加している。
④解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、官民一体となったテロ対策の推進を図るべきである。
消防は、警察などの関係機関や大規模集客施設・公共交通機関などの民間事業者、地域住民らと緊密に連携し、テロの脅威に対処する必要がある。
具体的には、官民連携による合同訓練の実施を強化することだ。
消防への事件発生の通報から、施設管理者による一般人の避難誘導、警察による突入およびテロ実行犯の制圧、消防による救急活動に至るまで、実践的な訓練を行うことが望ましい。
加えて、大規模集客施設や公共交通機関に対して、テロ対策の支援を強化する。
たとえば、適所にAEDや救急用具の設置を促すほか、施設従業員に対して応急処置の方法を講習することが有用であろう。
こうした取り組みを積極的に行い、有事の際に被害を最小限に留めるよう万全に準備しておくことが重要である。
第二に、テロ関連情報の収集および警戒体制の強化を図るべきである。
近年の多様化するテロ事件に対処するためには、的確な情報収集が欠かせない。
たとえば、過激化した個人によるテロ事件に使われる凶器として、爆弾や銃器ではなく、規制が緩く入手が容易な刃物や車両が増えている事実がある。
こうした情報は救急活動において有益だ。
したがって、消防は警察と連携し、外国で発生しているテロ事件に関する情報や、テロ対策上の着眼点について積極的に共有を図りたい。
加えて、そうした情報をもとに資機材の充実や訓練の強化を行うともに、スポーツや祭典など不特定多数の者が集まる各種イベントが開催される場合は、有事に備えて出動体制を整えておくことが求められるだろう。
⑤まとめ
私は消防官となり、テロ事件はいつ・どこで起こるか分からないという意識を持ち、日頃から自分に出来る限りの備えをしながら職務に励みたい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「⑥地域防災力」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
地域防災力を向上するため、消防はどのような取り組みを行う必要があるか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
地域防災力とは、災害から自分自身や家族の身を守る自助、地域の住民同士で助け合う共助により、災害を未然に防ぐとともに、災害発生時には被害を最小限に留める取り組みである。
②重大性
地域防災力の重要性は、これまでの災害で明らかになっている。
たとえば、糸魚川市の大火では、約150棟の家屋が焼失したにも関わらず、住民同士が声を掛け合い避難したことで、死者の発生を免れた。
したがって、地域防災力の向上に向けて、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、住民の防災意識の低下が懸念されることだ。
東京消防庁の調査によると、家具の転倒防止対策を実施していない理由として、「面倒である」を挙げる住民がもっとも多い。
第二に、地域コミュニティが衰退しつつあることだ。
少子高齢化や核家族化の進展に伴い、地域の助け合いが希薄化している。
④解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、住民の防災意識の向上を図るべきである。
個人で行える防災の取り組みとして、家具の転倒防止対策・感震ブレーカーの設置・消火器や火災報知器の設置など、有用なものは多い。
しかし、日々の忙しさや家具にキズを付けたくないという理由で、対策が普及しづらいことも事実だ。
そこで、消防は、より手軽に行える防災対策の周知に努める必要がある。
たとえば、家具をネジで強力に固定しなくとも、ポールやマットの器具を用いた安全かつ手軽な方法があることを、住民に広く発信する。
情報発信においては工夫を行いたい。
ホームページや広報誌のみならずSNSなど多様な手法で発信するほか、子ども連れで気軽に参加しやすい防災イベントの開催などの取り組みを積極的に行うことが重要である。
第二に、地域の防災活動を支援するべきである。
消防がリーダーシップを発揮し、希薄化しつつある地域による助け合いを再び強固なものにする必要がある。
具体的には、自治会や消防団と連携し、街歩きをしながら危険箇所を把握し、情報を書き込んで防災マップを作成する。
これにより、地域住民の連帯が強まるとともに、消防は地域の実態に応じた対策を検討できる。
次に、地域住民が一体となった防災訓練を繰り返し行うことが重要だ。
このとき、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な住民については救出する人を事前に決め、実際に救助を行うなど、地域の実情を踏まえたきめ細かな訓練をコーディネートする役割が、消防には求められる。
⑤まとめ
私は消防官となり、災害時に住民の命を守る責務を果たしながらも、平素から地域に密着した活動により地域防災力の向上に貢献したい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例「⑦消防団」

【消防官*東京消防庁】論文テーマ
消防団の活動を活性化するため、消防はどのような取り組みを行うべきか、あなたの考えを述べなさい。
【消防官*東京消防庁】論文模範解答例
①定義
消防団とは、地域住民らにより組織され、災害時に消火活動を担うほか、平時に住民へ防災意識の啓発を行う消防機関である。
近年、消防団の団員数は減少傾向にあり、全国で80 万人を下回る危機的な状況となっている。
②重大性
消防団員の減少は、どのような影響をもたらすか。
それは、地域防災力の低下が懸念されることだ。
近年、気候変動により災害は激甚化・頻発化している。
加えて、高齢化により、災害の犠牲になりやすい高齢者が増加している。
こうした状況において、消防だけで全ての住民の命を守ることは困難になりつつある。
したがって、地域防災力の中核である消防団の活動を活性化するため、消防は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、若年層の入団者数が減少していることだ。
第二に、核家族化の進展や共働き世帯が増加していることだ。
こうした住民は、従来の消防団の活動は負担が大きく参画が難しい。
④解決策
それでは、消防はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、消防団の意義を若年層に広報啓発するべきである。
消防団の活動の様子を住民に広く公開し、住民の理解を深めることで、消防団に興味を持つ若者を増やす取り組みを積極的に行うことが重要だ。
具体的には、消防操法大会の活用が考えられる。
操法大会は、消防団員の日頃の訓練の成果を災害時以外で披露する貴重な機会である。
消防は、消防団や地方公共団体と連携し、地域の祭りや行事で操法大会を同時に開催することで、住民にとって身近な地域のイベントとなるよう努めることが有用であろう。
このとき、情報発信の方法に工夫をしたい。
事前にホームページや広報誌でイベントを告知するのはもちろん、当日の観覧者に対して消防団をPRするチラシを配布したり、操法大会の動画をSNSで発信したりすることで、若い住民の印象に強く残ると期待される。
第二に、社会環境の変化に対応する柔軟な活動を支援するべきである。
消防団は、災害に備え様々な訓練や活動を行っており、消防団員にとって過大な負担となっているおそれがある。
こうした状況では、共働き世帯などが消防団に参画することは難しい。
したがって、消防は、真に必要な訓練や活動を精査し、効率的なスケジュールで実施できるよう消防団に対してサポートする姿勢が求められる。
加えて、機能別団員制度の推進を図るべきである。
機能別団員とは、全ての災害対応に従事する基本団員と異なり、特定の活動、たとえば大規模災害や広報活動のみに従事する団員である。
機能別団員であれば参画できる住民も多いだろう。
消防は、以上のような取り組みを、消防団と意見交換しながら積極的に進めていくことが重要である。
⑤まとめ
私は消防官となり、消防団の魅力を住民に広く伝え、消防団活動の活性化に貢献したい。