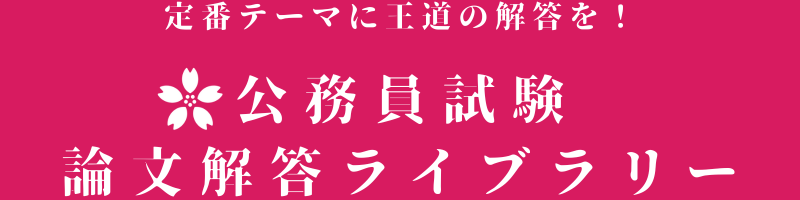こんにちは!
「定番テーマに王道の解答を! 公務員試験 論文解答ライブラリー」の編集長です。
このブログは、公務員採用試験の論文試験でよく出題されるテーマや、試験種ごとの論文試験の過去問について、模範解答例を紹介しています。
模範解答例を書いた人

旧帝大を卒業後、国家公務員として省庁で人事の仕事をしていました。
現在は退職し、公務員志望者の論文添削や面接指導などをおこなっています。
この記事では、国家公務員や地方公務員を問わず、あらゆる公務員試験で頻出テーマの模範解答例を紹介します。
論文テーマはこちら。
対象の試験区分はこちら。
模範解答例は、論文指導のプロが予備校の論文構成に準じて答案を書き、推敲を重ねた良質な答案です。
この模範解答例を読めば、答案を書くために必要な知識を効率的にインプットすることができます。
また、模範解答例をお手本にしながら自分で答案を書いてみることで、万全な論文対策が可能です。
これから受験を控える皆さんに、ぜひ活用してもらえると嬉しいです。
なお、もっとたくさんの模範解答例を読みたいという人は、こちらのnoteを活用してください。
出題が予想されるあらゆるテーマをカバーしているので、不足はありません。

【公務員試験】論文模範解答例「①災害」

【公務員試験】論文テーマ
災害発生時に住民を守るため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを述べなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
災害発生時における行政の役割は、住民の迅速な避難誘導を行うこと、避難生活の適切な支援を行うことが一義的に重要だ。
②重大性
災害による犠牲は、建物の倒壊や火災など直接的な被害によるものだけではない。
先の大震災では、災害そのものからは生き残ったにも関わらず、厳しい避難環境を原因とする犠牲が多くみられた。
したがって、災害時に住民を守るため、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、災害が頻発化していることだ。
実際、平成 28 年の熊本地震以降、多数の死傷者が生じる大規模災害が毎年のように発生している。
第二に、災害が激甚化していることだ。
それゆえ、多くの住民が長期間の避難生活を余儀なくされる。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、頻発化する災害に対して、住民が安全に避難できるよう平時から備えを図るべきである。
災害はいつ・どこで発生するか分からない。
有事の際に迅速な避難ができるよう準備しておく必要がある。
まず、地域の危険箇所に関する実態把握に努めるとともに、防災無線に異常はないか点検したり、避難指示の出し方を確認する努力を怠らないことが重要だ。
加えて、自治会と連携し避難訓練の実施を強化する。
このとき、消火器やタンカーを用いた実践的な訓練内容をコーディネートするほか、多様な住民の参加を呼び掛ける役割が行政には求められる。
ただし、一人暮らしの高齢者や身体の不自由な住民など、避難訓練への参加が困難な住民に対しては、可能な限り戸別訪問を実施し、避難方法の相談に乗るなどの配慮が必要であろう。
第二に、避難生活における安全・安心の確保に努めるべきである。
まず、支援物資の確保や分配を速やかに行うことが重要だ。
具体的には、地域の人口分布やハザードマップに基づく避難先を丁寧に分析し、必要な物資を平時から準備しておく。
ただし、備蓄しているだけでは、有事の際に適切な分配ができるとは限らない。
そこで、防災訓練を行う際に、災害発生から数時間後や数日後の状況を想定した対応をシミュレーションしておく必要がある
次に、避難住民の相談対応を強化することが重要だ。
災害発生時、避難所の担当職員と災害対策本部が緊密に連携し、避難所での生活が長期間にわたることから生じる様々な問題の解決に努める。
たとえば、被災者が貴重品の紛失を懸念しているようであれば、貴重品ロッカーの設置を検討することで被災者の安心が図られる上に、住民同士の無用なトラブルが避けられるだろう。
⑤まとめ
災害時における行政の役割の特徴は、発災当初から避難生活が終わるまでの長期間にわたり、地域住民に寄り添い続けることにある。
行政は、その期待と責任に応えなければならない。
私は行政職員となり、日頃から地域に根差した防災活動に取り組み、災害から住民を守ることに貢献したい。
【公務員試験】論文模範解答例「②少子化」

【公務員試験】論文テーマ
少子化の改善を図るため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
少子化とは、合計特殊出生率が人口置換水準2.1を長期間にわたって、相当程度下回っている状態である。
我が国の出生率は低下傾向であり、令和3年は全国1.3であった。
②重大性
少子化は地域にどのような影響をもたらすか。
第一に、地域の人口が減少することだ。
とりわけ、生産年齢人口の減少による地域経済の衰退が懸念される。
第二に、地域の高齢化が進むことだ。
高齢化により、社会福祉費の増大が見込まれる。
したがって、少子化の改善を図るため、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、非婚化が進行していることだ。
近年、夫婦の子ども数は微減に留まるが、非婚率は著しく上昇している。
したがって、出生率低下の主因は非婚率の上昇といえる。
さらに、非婚化の主因は若年者の生活や雇用が不安定化したことにある。
実際、正規労働者か非正労働者かによって結婚率に大きな差がある。
第二に、若年女性人口の減少が予想されることだ。
若年女性が減少する地域は、出生率が大幅に改善したとしても出生数は減少し続け、少子化は止まらない。
現在、地方から東京圏に若年女性が顕著に流出している。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、若年者の雇用と生活の安定化を促進し、非婚率の改善を図るべきである。
まず、雇用の安定については、望まない非正規労働者の正規化が王道である。
正規化する取り組みを実施した事業者に対して、国は助成金を支給している。
したがって、行政は広報誌や商工会議所を活用し、こうした施策の周知広報を強化する。
なお、助成金の申請や人事・労務に関して悩みがある事業者に対しては、社会保険労務士が無料で相談を受ける機会を提供すると有用だろう。
次に、生活の安定については、暮らしの基盤となる住居の存在が欠かせない。
とりわけ、雇用保険の加入率が低い非正規労働者は、病気や怪我により休職し、家賃を払えず住居を容易に失う恐れがある。
若年者が生活に困窮する前に、一定の要件を満たす若年者に対し家賃補助を行うことは検討に値する。
第二に、若年女性が働きやすく暮らしやすい環境を整備し、若年女性人口の減少を防止するべきである。
まず、働きやすい環境整備については、若年女性の多様化する就業ニーズを満たすことが重要だ。
したがって、行政は産業関係団体と連携し、女性活躍に取り組む企業の周知広報を強化する。
このとき、女性目線による企業の紹介や、女性の幹部職員比率・男性の育児休業取得率などの情報を公表する視点が欠かせない。
一方、キャリアアップを望まない女性が増加していることに留意が必要だ。
いわゆる「ゆるキャリ」志向の女性が働きやすい企業を交えて紹介することが望ましい。
次に、暮らしやすい環境整備については、ワークライフバランスの実現を図る。
行政は、ワークライフバランスに関する講座や研修会を積極的に開催するべきだ。
このとき、意欲ある事業者に対しては、アドバイザーを無料で派遣する取り組みが有効であろう。
⑤まとめ
以上、行政は若年者の生活・雇用の安定化、および若年女性の定住環境の整備に係る取り組みを一層強化するべきである。
私は行政職員となり、少子化の改善に貢献する所存である。
【公務員試験】論文模範解答例「③健康増進」

【公務員試験】論文テーマ
健康寿命の延伸を図るため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく、元気に自立して暮らすことができる期間である。
②重大性
健康寿命延伸の重大性はなにか。
それは、住民一人ひとりの生活の質が向上するとともに、行政の医療・介護関係経費の支出抑制につながることだ。
したがって、健康寿命の延伸に向けて、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
少年期においては、健全な生活の送り方を教育する家庭の役割が低下していることだ。
核家族化の進展や共働き世帯の増加により、朝食を抜く機会が増えたり、親子でスポーツを楽しむ時間が減少したりしている。
成人期においては、喫煙・過度な飲酒・運動不足など生活習慣の乱れから、疾病を発症する人が多くなることが課題である。
高齢期においては、社会的な孤立が深刻化していることが挙げられる。
仕事を持たず地域社会との関わりが薄い高齢者は、運動・認知機能が低下しやすい。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
少年期については、学校や地域社会において子どもが健康的な食習慣・運動習慣を身に付けられるよう支援するべきである。
学校においては、給食を教材として活用しながら関連教科で食に関する教育活動を推進する。
児童生徒が心身の成長や健康の増進に望ましい栄養や食事の取り方を理解し、自ら管理していく能力を養うことが肝要だ。
地域社会においては、地域のスポーツクラブに子どもの参加を促し、運動の楽しさを実感できるよう取り組む。
たとえば、地域のクラブ活動の情報を集約して周知したり、活動場所として学校の校庭や体育館を放課後や土日に開放したりすると、子どもは安心して参加しやすいだろう。
成人期については、がん検診・特定検診の受診を促進し、疾病の早期発見と生活習慣の改善を図るべきである。
現状、主ながん検診の受診率は5割程度に留まる。
したがって、検診の受診を市民に広く周知するとともに、企業に対して従業員へ受診の呼び掛けを要請することが重要だ。
受診の動機付けとして、何らかの特典が受けられる健康マイレージ事業の推進が有用であろう。
検診の結果、異常が確認された場合は生活習慣の改善が必要になる。
これを個人の努力に任せるのではなく、保健師が栄養バランスのとれた食事・適度な運動・禁煙などの取り組みをサポートする体制を整える役割が、行政には求められる。
高齢期については、仕事や地域社会との関係性を失わないよう環境を整備するべきである。
65歳以上であっても労働意欲を持った「元気な高齢者」は数多く存在する。
そこで、定年を廃止または70歳以上に引き上げた企業に対して、奨励金を支給し高齢者雇用の機会を増やすことが重要だ。
加えて、地域住民同士の交流の機会を積極的に設けたい。
たとえば、社会福祉法人と連携し、福祉施設のロビーを会場として高齢者がお茶を楽しんだり、モニターに動画を映して全員で体操したりできる取り組みを行うことで、住民同士が顔を合わせながら交流を深められる。
高齢期においても仕事や地域社会で積極的に活動することで、運動機能や認知機能の低下を抑制することが可能だ。
⑤まとめ
地域社会において高齢化が進む中、健康寿命の延伸はますます重要となっている。
私は行政職員となり、市民だれもが健康に暮らせるよう粘り強く対策に励みたい。
【公務員試験】論文模範解答例「④産業振興」
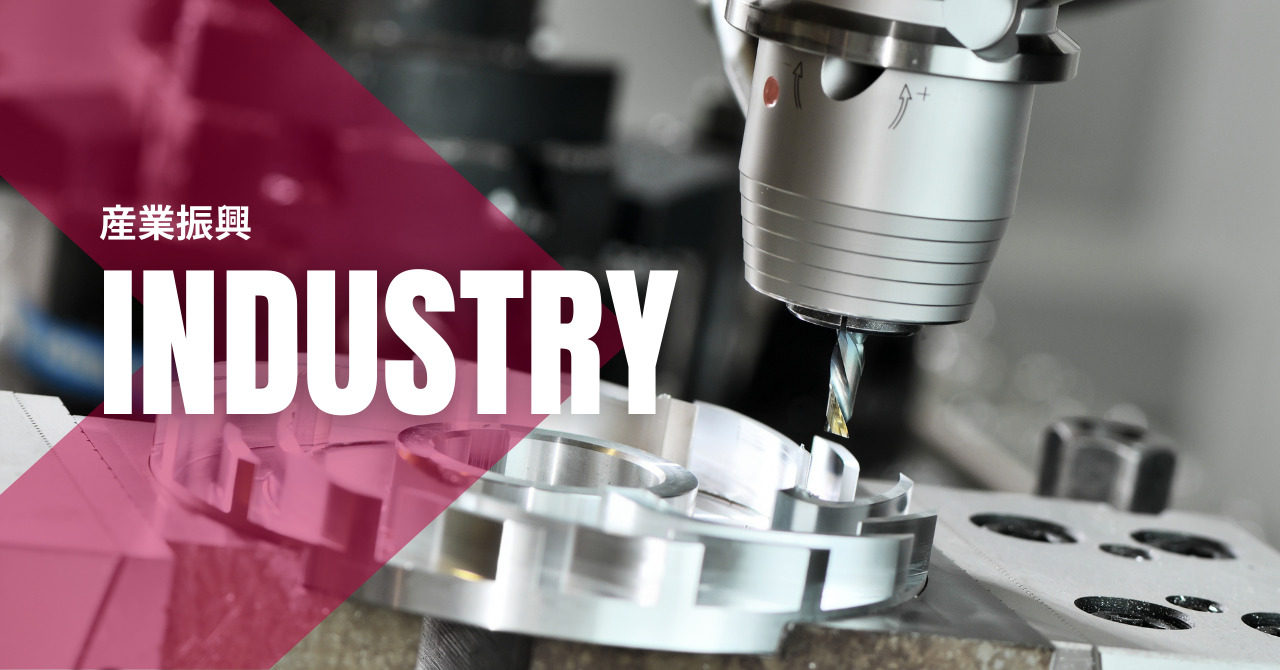
【公務員試験】論文テーマ
産業振興を推進するため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
産業振興とは、企業の競争力強化および経営の安定化を図り、地域経済の健全な発展と市民生活の向上を目指す取り組みである。
②重大性
なぜ、産業振興が求められているのか。
それは、地域住民の雇用と暮らしを守るためだ。
地域社会には、高度な技術を持つ町工場や個性的な商店など、様々な中小企業が集積している。
こうした中小企業が雇用の大部分を占めるとともに、活気ある街並みと市民の日常生活を支えているのだ。
したがって、産業振興の推進に向けて、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、市場環境が悪化していることだ。
物価や人件費の高騰に加えて、グローバル化やインターネット販売の拡大により受注競争が激しさを増している。
第二に、生産年齢人口の減少が見込まれることだ。
少子化の進展により、中小企業の慢性的な人材不足が深刻化する懸念がある。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、中小企業の生産性向上を支援し、競争力強化を図るべきである。
とはいえ、企業の業種や抱える問題は様々だ。
したがって、どのような企業でも実行でき、なおかつ効果が見込める支援策を検討する必要がある。
たとえば、業務効率化を通して生産性を高める活動である「カイゼン」の普及促進が挙げられる。
カイゼンは大手メーカーでは一般的だが、その他の業種でも企業規模を問わず有効な取り組みだ。
そこで、産業関係団体と連携し、経営者や幹部を対象にカイゼンの専門家による研修を実施する。
一方、生産性向上にはICTの導入が欠かせない。
現在、販売管理システムや労務管理システムなどのITツールが数多く開発されている。
しかし、ICTの導入にはコストが掛かる上に、どんなツールを選択するべきか判断する知識が必要だ。
そこで、導入コストを補助することが考えられるが、国が様々な補助金を用意しているため、これを活用する。
地方自治体においては、節約した予算でICT導入のアドバイザーを企業に派遣する取り組みを行うと有用である。
第二に、中小企業の人材確保を支援し、経営安定化を図るべきである。
まず、中小企業で働く魅力を広く発信したり、就職フェアを開催したりすることはもちろん重要だ。
しかし、それだけでは十分ではない。
なぜなら、求職者は大手志向が強い上に、あらゆる企業が人材不足のため採用活動に力を入れているからだ。
そこで、潜在的な労働力の掘り起こしを行う必要がある。
具体的には、一人親や引きこもりの若者を支援するNPOと連携し、彼らが中小企業で働きながら必要な技術や資格を取得し、正社員として定着できる取り組みを推進したい。
このとき、行政は予算的な基礎付けを確保し、現場の活動はNPOの助けを借りるなど役割分担を行う。
さらに、学校と協力し、子ども達に工場見学や商店街散策などの機会を提供することが重要だ。
これにより、地域産業への親近感が醸成され、地域の中小企業の未来を担う人材が育まれるだろう。
⑤まとめ
企業活動は、市場における自由競争が原則だ。
しかし、中小企業は地域経済の基盤を担う重要な存在である。
私は行政職員となり、生産性向上や人材確保などの核心的な支援に貢献したい。
【公務員試験】論文模範解答例「⑤地球温暖化」

【公務員試験】論文テーマ
地球温暖化を防止するため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
地球温暖化とは、大気中の温室効果ガスの濃度が人間活動により上昇し、温室効果が高まることにより地球の気温が上がる現象である。
現在、地球の平均気温は上昇傾向にあり、我が国は2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを目指している。
②重大性
地球温暖化の重大性はなにか。
それは、地球環境に不可逆的な変化が生じることだ。
世界各地では記録的な熱波や寒波による被害が生じているほか、我が国においてもゲリラ豪雨など異常気象が起こり始めている。
したがって、地球温暖化の防止に向けて、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
それは、地球温暖化問題の解決は長期にわたるため、住民や企業が継続して環境に配慮した行動に取り組まなければならないことだ。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、住民がやりがいを持って活動できる環境を整えるべきである。
環境保護を呼び掛けることは重要だが、それだけでは実践に結び付かない場合が多いだろう。
したがって、住民の自発的かつ継続的な活動を促進するため、達成感が得られる仕掛けを工夫して施す必要がある。
たとえば、電気・ガス・水道の使用料を記録し、二酸化炭素排出量を計算する「環境家計簿」をつける取り組みを推奨することが有用である。
この取り組みにより、自らが排出する二酸化炭素量を自覚し、無駄なエネルギー消費を控えようとする意識が高められる。
加えて、取り組みを継続するとエコグッズと交換できる仕組みにすると、より効果的であろう。
第二に、企業が参画しやすいようインセンティブを提供するべきである。
まず、企業に対して省エネ設備の普及促進を図ることが重要だ。
しかし、中小企業の多くは資金不足から省エネ設備の導入に踏み出せない実情がある。
したがって、設備を導入する企業には可能な限り補助金を交付する必要があろう。
さらに、企業の温暖化防止に向けた努力が利益につながる仕組みがあれば、自発的に脱炭素経営に取り組む企業が増えると期待される。
たとえば、優れた取り組みを行って二酸化炭素の排出削減を実現した企業名を公表・表彰したり、省エネに取り組む企業を認定したりして、企業の社会的な評価を高めることが有用だ。
⑤まとめ
地球温暖化防止は喫緊の課題である。
住民や企業が二酸化炭素の排出責任を自覚し、継続的に二酸化炭素削減に取り組むための支援をする役割が行政には求められる。
私は行政職員となり、様々な主体に脱炭素社会の実現を粘り強く働きかけたい。
【公務員試験】論文模範解答例「⑥地域コミュニティ活性化」

【公務員試験】論文テーマ
地域コミュニティを活性化するため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
地域コミュニティとは、日常生活のふれ合いや共同の活動、共通の体験を通して連帯感や信頼関係が築かれている地域社会、すなわち「近所同士のつながり」である。
近年、地元への帰属意識の低下や個人主義の進展により、地域コミュニティは希薄化しつつある。
②重大性
地域コミュニティの希薄化はどのような影響をもたらすか。
一つに、社会的に孤立する人が増加することだ。
様々な問題や悩みを一人で抱えることで、児童虐待や自殺につながるおそれがある。
加えて、住民同士のコミュニケーション不足により、地域の防犯・防災機能の低下が懸念される。
したがって、地域コミュニティの活性化に向けて、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、フォーマルな地域コミュニティの代表である町会・自治会の活動が衰退しつつあることだ。
実際、町会・自治会の加入率は全国的に低下傾向にある上、参加者の高齢化や担い手不足が深刻である。
第二に、近所の住民同士が顔見知りになって交流する機会が減少していることだ。
それに伴い、ママ友や高齢者のお茶飲みグループなど、インフォーマルな地域コミュニティを形成するきっかけが喪失している。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、町会・自治会に対する現役世代の関心を高めるとともに、現役世代が活動に参加しやすい環境づくりを支援するべきである。
まず、町会・自治会の活動内容の写真や参加者の声を紹介する広報誌を作成し、ホームページやSNSで広く発信する。
このとき、町会・自治会は防犯・防災、環境美化など住民生活と密接に結び付いた活動を担っていることを積極的に周知し、現役世代の関心を高めることが重要だ。
一方、現役世代は仕事や家事で忙しく、活動に参加したくてもできない事情がある。
そこで、現役世代が気軽に参加できる仕組みづくりを支援する必要がある。
たとえば、防犯パトロールやごみ拾いなどの活動単位で参加者を募集する取り組みを町会・自治会に提案したい。
一度活動に参加してみることで地域課題に興味を持ち、その後も継続して関わろうとする住民が増えると期待される。
第二に、地域住民が気軽に交流できる場づくりを行うべきである。
まず、既存のコミュニティを支援することから始めるのがよい。
地域には子育てする母親の集まるサークルや、祭りなどの住民交流イベントを実施する団体が存在する。
そこで、これらのコミュニティが積極的に活動し、地域住民同士の交流が促進されるよう支援することが重要だ。
たとえば、活動場所を提供したり、コミュニティの活動内容を広報誌でPRすると、参加者が増えてコミュニティの輪が広がっていくだろう。
次に、新たなコミュニティの創出に取り組みたい。
既存のコミュニティだけでは、身体の不自由な高齢者や障害のある子どもなどが十分に内包されない可能性がある。
したがって、NPOや社会福祉法人と連携し、認知症カフェを備えた地域の多世代交流拠点や、障害を持つ子どもの放課後の居場所を整備し、社会的弱者が地域コミュニティから疎外されないよう留意しなければならない。
⑤まとめ
地域コミュニティの活性化は、一朝一夕に成し得ない。
私は行政職員となり、地域に対する現役世代の関心を高めること、住民が活きいきと交流できる場を整えることに粘り強く励みたい。
【公務員試験】論文模範解答例「⑦住民参加」

【公務員試験】論文テーマ
住民参加を促進するため、行政はどのように取り組むべきか、あなたの考えを論じなさい。
【公務員試験】論文模範解答例
①定義
住民参加とは、行政が市政・県政情報を住民に発信し説明責任を果たすことにより住民と行政運営の施策や課題を共有し、住民から政策提案や要望を収集するとともに、住民と行政が協働で地域課題の解決を図ることである。
②重大性
なぜ、住民参加の促進が求められているのか。
それは、住民の行政ニーズが多様化しているからだ。
少子高齢化の進展や生活様式の変化を背景として、地域課題は多様化しつつある。
こうした要望を行政が単独で把握・対処することは困難である。
したがって、住民参加の促進に向けて、行政は一層の取り組みを行う必要がある。
③課題
取り組みを行うにあたり、課題はなにか。
第一に、行政に対する住民の意識が希薄なことだ。
理由として、行政からの情報発信は難解になりがちなことや、行政への意見表明は成果を感じづらいことが挙げられる。
第二に、協働による課題解決の担い手が十分ではないことだ。
住民参加というと、「避難訓練に参加」など行政主体のイベントに住民が協力するに留まる場合が多い。
④解決策
それでは、行政はどのような取り組みを行う必要があるか。
第一に、広報広聴の強化を図るべきである。
行政に関する情報を住民に届ける広報と、住民の意見を受けとめる広聴の活用により、住民とのコミュニケーションを円滑化し信頼関係を育むことが、住民参加の土台となる。
まず、分かりやすく丁寧な広報に努めたい。
具体的には、専門用語や常用ではない表現を用いるのではなく、誰が見ても理解しやすい言葉で表現することが重要である。
加えて、行政職員の写真を広報誌に掲載しセリフ調で情報を紹介したり、イラストの得意な職員が描いたキャラクターをホームページに登場させたりすると、より関心を持って行政に親しんでもらえるはずだ。
さらに、迅速かつ応答性の高い広聴に努めたい。
現状として、審議を通して大方の方針が決まっている施策の場合、パブリックコメントで意見を募っても反映が見られないことがある。
こうした状況では、住民は参画に意義を感じないだろう。
したがって、政策立案の初期段階からタウンミーティングの開催やアンケート調査を行い、住民の意見を積極的に収集することが重要である。
加えて、得られた声がどのように新しい施策や決まり事に反映されたのか、ホームページや広報誌で分かりやすく周知すると、継続して意見を述べる意欲が高まるはずだ。
第二に、住民がやりがいを持って協働に参画できる環境を整えるべきである。
協働を呼び掛けることは重要だが、それだけでは実践に結び付かない場合が多いだろう。
したがって、住民の自発的で継続的な参画を促進するよう、協働において達成感が得られる仕掛けを工夫して施す必要がある。
具体的には、スキルのある民間事業者を巻き込んだ取り組みが有用である。
つまり、まちづくりに知見の深い企業と連携しノウハウを指導してもらいながら、住民によるボランティア活動の促進を図るのだ。
実際、ある自治体では住民の発案により、無印良品を展開する企業をコーディネーターとして迎え、空きの目立つ商店街の再生に取り組んだ。
誰でも気軽に集まれるジャズ喫茶を地域住民と共に立ち上げ、行政が積極的に広報したことで、定期的にライブが開かれ商店街に活気が見られるようになったという。
行政職員は、住民がやりがいを持って協働に取り組める環境を整備するよう、努める必要がある。
⑤まとめ
私は行政職員となり、住民の声に耳を傾けて信頼関係を築き、住民と協働しながら地域課題の解決に貢献したい。