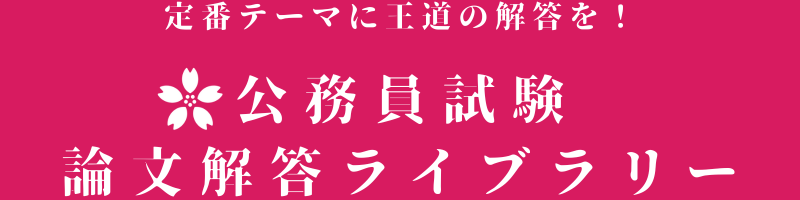こんにちは!
「定番テーマに王道の解答を! 公務員試験 論文解答ライブラリー」の編集長です。
このブログは、公務員採用試験の論文試験でよく出題されるテーマや、試験種ごとの論文試験の過去問について、模範解答例を紹介しています。
模範解答例を書いた人

旧帝大を卒業後、国家公務員として省庁で人事の仕事をしていました。
現在は退職し、公務員志望者の論文添削や面接指導などをおこなっています。
この記事では、国家公務員一般職の論文試験の過去問について、模範解答例を紹介します。
模範解答例は、論文指導のプロが予備校の論文構成に準じて答案を書き、推敲を重ねた良質な答案です。
この模範解答例を読めば、答案を書くために必要な知識を効率的にインプットすることができます。
また、模範解答例をお手本にしながら自分で答案を書いてみることで、万全な論文対策が可能です。
これから受験を控える皆さんに、ぜひ活用してもらえると嬉しいです。
【国家一般職】論文模範解答例「2022年過去問:カーボンニュートラル」

【国家一般職】論文テーマ
我が国は、2020年10月に、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言した。
また、2021年4月には、2030年度の新たな目標として、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指し、さらに50%削減に向けて挑戦を続けるとの新たな方針を示した。
なお、世界では、120以上の国と地域が2050年までのカーボンニュートラルの実現を表明している。
※カーボンニュートラルとは、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること
上記に関して、以下の資料①、②を参考にしながら、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。
(1)カーボンニュートラルに関する取組が我が国にとって必要な理由を簡潔に述べなさい。
(2)カーボンニュートラルを達成するために我が国が行うべき取組について、その課題を踏まえつつ、あなたの考えを具体的に述べなさい。
【国家一般職】論文模範解答例
(1)
カーボンニュートラルに関する取組が我が国にとって必要な理由は、第一に地球温暖化対策、第二に経済活性化のためである。
近年、急激な気候変動により世界各地では異常気象の発生や生態系の破壊が起きており、このままでは不可逆的な変化が生じる懸念がある。
その原因とされるのが、温室効果ガスの増加だ。
したがって、世界各国が協力して温室効果ガスの削減に取り組み、持続可能な地球環境を維持する必要がある。
一方、カーボンニュートラルに関する技術開発は経済の活性化をもたらす。
長年の経済低迷に苦しむ我が国にとって、この分野を成長産業とし、経済の再活性化を目指すことが重要だ。
(2)
カーボンニュートラルを達成するために我が国が行うべき取組はなにか。
第一に、再生可能エネルギーの普及促進を図るべきである。
資料①の通り、電力部門は排出量全体の約4割を占めており、排出削減が欠かせない。
資料②の通り、我が国の主要電力である火力発電はCO2排出量が著しく大きいため、排出量が小さい再生可能エネルギーに電力源を分散する必要がある。
しかし、課題は再生可能エネルギーの発電コストが高いことだ。
たとえば、太陽光発電パネルの設置費用は高額なため、導入をためらう住民や企業は多い。
したがって、再生可能エネルギーを導入する住民や企業に対し、経済的な負担を軽減することが重要だ。
具体的には、太陽光発電や地熱発電の設備を設置する際に補助金を支給するほか、設備の研究を行う大学や企業との産学連携を促進し、安価な設備の開発に取り組むと有用であろう。
第二に、住民や企業の自発的かつ継続的な排出削減を支援するべきである。
資料①の通り、非電力部門は民生・産業・運輸部門からなる。
つまり、各主体が排出責任を自覚し、長期的に排出削減活動に取り組むよう働き掛ける必要がある。
しかし、課題は環境保護を呼び掛けるだけでは、実践に結び付かないことだ。
したがって、住民や企業が参画しやすいようインセンティブを提供することが重要だ。
住民に対しては、電気・ガス・水道の使用料を記録し、CO2排出量を計算する「環境家計簿」をつける取り組みを推奨する。
この取り組みにより、自らが排出するCO2量を自覚し、無駄なエネルギー消費を控えようとする意識が高められる。
加えて、取り組みを継続するとエコグッズと交換できる仕組みにすると、より効果的であろう。
企業に対しては、温暖化防止に向けた努力が利益につながる仕組みがあれば、自発的に脱炭素経営に取り組む企業が増えると期待される。
そこで、優れた取組を行って排出削減を実現した企業名を公表・表彰したり、省エネに取り組む企業を認定したりして、企業の社会的な評価を高めることが有用だ。
こうした取り組みにより、カーボンニュートラルを実現し、温暖化対策と経済活性化の両立を目指すべきである。
【国家一般職】論文模範解答例「2021年過去問:子どもの貧困」

【国家一般職】論文テーマ
厚生労働省「国民生活基礎調査」による我が国の「子どもの貧困率」は、2018年時点で13.5%と、子どもの約7人に1人が貧困線”を下回っている。
このような状況に関して、以下の資料①、②、③を参考にしながら、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。
なお、同調査における「子どもの貧困率」とは、17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない17歳以下の子どもの割合のことである。
※貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の値をいい、等価可処分所得とは、下記により算出した所得である。なお、2018年の貧困線は127万円である。
等価可処分所得=(総所得一拠出金(税金や社会保険料))÷√世帯人員数(所得のない子ども等を含む)
(1)我が国の子どもの貧困問題が社会にどのような影響を及ぼすのか、子どもの貧困に関する現状を踏まえながら、あなたの考えを述べなさい。
(2)我が国が子どもの貧困問題に取り組む上でどのようなことが課題となるかについて、あなたの考えを具体的に述べなさい。
【国家一般職】論文模範解答例
(1)
子どもの貧困に関する現状として、資料①の通り子どもの貧困率は横ばいで改善が進んでいない。
とりわけ、大人が一人の貧困率は緩やかに改善しているものの、依然として半数近くが貧困状態にある。
子どもの貧困問題は社会にどのような影響をもたらすか。
一つに、経済活力の低下が挙げられる。
資料②の通り、生活保護世帯や児童養護施設で暮らす貧困状態にある子どもは、そうでない子どもに比べて大学等の進学率が著しく低い。
最終学歴の差は生涯収入を大きく左右する。
つまり、子どもの貧困が教育格差を生み、将来の収入格差につながることで、社会にとって税収の減少と消費活動の低迷として大きな影響をもたらす。
(2)
子どもの貧困問題に取り組む上で課題はなにか。
第一に、親の就業を安定化させる必要があることだ。
資料①および③の通り、母子世帯の親は約2割が非就業であるほか、就業している場合でも約半数が収入の低い非正規職員であることから、母子世帯の子どもは約2人に1人が貧困の状態にある。
したがって、国は一人親家庭に理解のある企業を増やし、就業希望者とのマッチングを図る取組に力を入れるべきである。
加えて、人材不足の深刻化が見込まれる介護業界と連携し、一人親が介護関連の資格を取得した上で、正規職員として働けるよう環境を整えることが有効であろう。
ただし、無就業の親は過去に何度も解雇されたり就職に失敗したりして、自信を失っている可能性がある。
そこで、職業訓練で履歴書の書き方や面接の受け方を丁寧にサポートする配慮が重要だろう。
第二に、子どもの見守り体制を拡充する必要があることだ。
貧困状態にある子どもは、学習状況や健康状態に関して親の気遣いが見込めない場合がある。
こうした子どもを学校で早期発見し、各自の状態に合わせて適切な支援を施さなければならない。
このとき、業務過多な教師に代わって、学校と福祉機関の連携を担うスクールソーシャルワーカーの存在が重要となる。
しかし、資料③の通り、スクールソーシャルワーカーによる対応実績のある学校の割合は半数程度に留まっており、積極的な活用が課題だ。
したがって、国は専門人材の育成に力を入れるほか、先進的な対応事例やノウハウを広く共有するべきである。
一方、子どもの様子や変化を見守る体制は、スクールソーシャルワーカーだけで十分とは言い切れない。
そこで、当事者により近い存在であり、きめ細かな支援を得意とするNPOと協働することが有効であろう。
つまり、子どもの学習支援や母子家庭の支援を行うNPOを相談窓口とし、問題を整理した上で、しかるべき行政支援につなげるのである。
国は予算的な裏付けを整え、NPOの活動を支援するとよい。
子どもの貧困問題の解決は、長期的に我が国の経済活性化につながる。
親・子ども・学校など幅広い支援が必要である。
【国家一般職】論文模範解答例「2020年過去問:健康寿命」

【国家一般職】論文テーマ
我が国では、2040年頃には、いわゆる団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢者人口がピークを迎える一方、現役世代が急激に減少する。
そこで、2018年10月に設置された「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」の取りまとめにおいて、「健康寿命延伸プラン」が作成され、2016年時点において男性では72.14年、女性では74.79年となっている健康寿命を、2040年までに男女ともに3年以上延伸し、75年以上にすることが目標として掲げられた。
なお、健康寿命とは、平均寿命から寝たきりや認知症など介護状態の期間を差し引いた期間である。
このような状況に関して、以下の図①、②、③を参考にしながら、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。
(1)我が国が健康寿命の延伸に取り組む必要性について、あなたの考えを述べなさい。
(2)健康寿命の延伸を阻害する要因は何か。また、健康寿命を延伸するために国としてどのような取組が必要となるか。あなたの考えを具体的に述べなさい。
【国家一般職】論文模範解答例
(1)
我が国が健康寿命の延伸に取り組む必要性は何か。
第一に、介護関係経費の抑制につながることだ。
図①の通り、平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約12年であり、近年ほとんど変化していない。
健康寿命が延伸して平均寿命と健康寿命の差が縮まれば、介護を受ける期間が短縮し、介護関係経費の抑制が見込める。
少子高齢化が深刻化する我が国にとって、社会保障費の支出を削減する意義は大きい。
第二に、経済の活性化をもたらすことだ。
図②の通り、75歳以上まで就労意欲を持つ高齢者が全体の約6割を占めている。
健康寿命が延伸して高齢者の就労が増加すれば、消費活動の増大が見込める。
加えて、生産年齢人口の減少により人材不足が懸念される我が国にとって、高齢者の就労は不可欠である。
したがって、国は健康寿命の延伸に取り組まなければならない。
(2)
健康寿命の延伸を阻害する要因は何か。
第一に、生活習慣の乱れが蓄積し生活習慣病を発症すること、第二に、日々の活動量が低下し認知症を発症することである。
図③の通り、介護が必要になった主な原因のうち、脳卒中や心臓病などの生活習慣病に起因するものが約2割、認知症に起因するものが約2割を占める。
したがって、これらへの対策により健康寿命の延伸が期待できる。
それでは、国はどのような取組を行う必要があるか。
第一に、国民に対して生活習慣の改善を促し、生活習慣病の発症を予防するべきである。
現代は惣菜や外食を利用する傾向が強く、栄養バランスに偏りが生じやすいほか、喫煙や過度な飲酒、運動不足などで生活習慣が乱れやすい。
そこで、生活習慣改善の必要性や健康的な食生活、適度な運動など具体的な手立てを国民に広く紹介することが重要だ。
加えて、がん検診・特定検診の受診をきっかけとして、生活習慣の自発的な改善を促すと有効であろう。
しかし、主ながん検診の受診率は約5割に留まるのが現状だ。
したがって、検診の受診を国民に周知するとともに、企業に対して従業員へ受診の呼び掛けを要請するとよい。
第二に、企業に対して高齢者雇用の支援を強化し、認知症の発症を予防するべきである。
認知症は日々の活動量が低下することに起因する場合が多い。
したがって、高齢者の就労意欲の高さへの対応と合わせて、高齢者雇用の機会を増やす取組が求められる。
まず、定年を廃止または70歳以上に引き上げた企業に対して奨励金を支給し、多様な企業の参画を促す。
加えて、高齢者雇用の実施方法や配慮事項などのノウハウの提供を行うほか、バリアフリー設備の導入に補助金を支出し、高齢者の就業環境を整えることが重要だ。
高齢期においても社会で積極的に活動することで、認知機能の低下を抑制することが見込めるだろう。
元気な高齢者の増加は、社会保障費の削減や経済の活性化につながる。
国は上記の取組を通じて、健康寿命の延伸を実現する必要がある。
【国家一般職】論文模範解答例「2018年過去問:生産年齢人口の減少」
【国家一般職】論文テーマ
我が国の生産年齢人口は1990年代をピークに減少を続けており、今後も減少が続くと推計されている。この生産年齢人口の減少に伴う生産力の低下によって、我が国の社会経済に大きな影響を与えることが懸念されている。この状況に関して、以下の問いに答えなさい。
(1)生産年齢人口の減少による生産力低下に影響されることなく、中長期的に経済成長を実現していくために解決すべきと考える課題を、以下の図①、②を参考にしながら、二つ述べなさい。
(2)(1)で挙げた二つの課題を解決するためには、それぞれどのような取組が必要となるか。あなたの考えを具体的に述べなさい。
【国家一般職】論文模範解答例
(1)
第一に、高齢者の就業が進んでいなことである。
図①の通り、ほぼ全年代で女性の労働力人口比率は男性を下回っていることや、高齢者の労働力人口比率は男性・女性ともに急減していることが読み取れる。
女性の社会進出を一層促進する環境の整備は重要であるが、生産年齢人口の減少傾向が続く中、増加が見込まれる高齢者が働きやすい環境を整えることが喫緊の課題と言える。
第二に、労働生産性が向上していないことである。
図②の通り、先進諸国と比べて我が国の実質労働生産性は低水準にある。
原因として、
(2)
それでは、国はどのような取組を行う必要があるか。
第一に、高齢者が活躍できる就業環境を整備するべきである。
65歳以上であっても就業意欲を持った「元気な高齢者」は数多く存在する。
そこで、元気な高齢者の社会参加を促し、生産活動への従事を図ることが重要だ。
具体的には、定年を廃止または70歳以上に引き上げた企業に対して、奨励金を支給し高齢者雇用の機会を増やす。
加えて、就業意欲のある高齢者とそれを求める事業者をマッチングする相談会を、ハローワークなどを通じて開催することが有用である。
このとき、高齢者に対するサポートが欠かせない。
もともと高い技術や知識を持つ高齢者は多いが、人材不足が深刻な保育施設や介護施設などの新たな環境で働く場合も多いだろう。
したがって、高齢者に対して実地研修や個別面談を行い、福祉施設の補助などの仕事でいきいきと働けるよう支援する必要がある。
第二に、労働者一人ひとりが高い付加価値を生み出すよう支援するべきである。
生産性の向上に関する取り組みは、企業の業種や規模によって内容が異なると予想される。
したがって、どのような企業でも実行でき、なおかつ効果が見込める支援策を検討する必要がある。
具体的には、ICTの導入が挙げられる。
現在、販売管理システムや労務管理システムなどのITツールが数多く開発されている。
しかし、ICTの導入にはコストが掛かる上に、どんなツールを選択するべきか判断する知識が必要だ。
そこで、導入コストを補助するほか、希望する企業に対してICT関連のアドバイザーを派遣する取り組みを行うと有用であろう。
また、業務効率化を通して生産性を高める活動である「カイゼン」の普及促進が、生産性向上に大きく寄与すると考えられる。
カイゼンは大手メーカーでは一般的だが、その他の業種でも企業規模を問わず有効な取り組みだ。
産業関係団体と連携し、経営者や幹部を対象にカイゼンの専門家による研修を繰り返し実施する必要があるだろう。
生産年齢人口の減少が続く我が国において、高齢者の労働参加と生産性の向上は重要な課題である。
国は上記の取り組みを通して、持続的な経済成長を実現しなければならない。
【国家一般職】論文模範解答例「2015年過去問:言葉の変化」
【国家一般職】論文テーマ
文化庁「国語に関する世論調査」(平成25年度)によると、言葉や言葉の使い方に対する社会全体の関心が「以前よりも低くなっていると思う」という回答が30代から60代で5割を超えており、言葉や言葉の使い方に関する社会全体の知識や能力が「以前よりも低くなっていると思う」という回答が20代から50代で6割以上となっています。
また、「世間ずれ」、「やぶさかでない」といった慣用句等の意味を尋ねたところ、本来とは違う意味とされる選択肢の方が多く選択される状況にあります。
さらに「~る」、「~する」形の動詞については、「チンする」(「電子レンジで加熱する」という意味)は9割、「サボる」(「なまける」という意味)は8割台半ばの人が「使う」と回答しています。
他方、国連教育科学文化機関(ユネスコ)が2009年に発表した「世界消滅危機言語地図」においては、世界で2,500に上る言語が消滅の危機にあると指摘されており、日本国内ではアイヌ語や沖縄語など8言語・方言がその中に含まれています。
(1)言語の意味の変化、新しい言葉の出現、言葉の消滅が起こる原因及び影響として考えられるものを挙げた上で、それらを踏まえて、言葉の果たす役割について、あなたの考えを具体的に述べなさい。
(2)言葉についての関心を喚起し、理解を深めるための施策について、あなたの考えを述べなさい。
【国家一般職】論文模範解答例
(1)
言葉の意味の変化、新しい言葉の出現、言葉の消滅が起こる原因として、情報化社会の進展が挙げられよう。
インターネットを介したコミュニケーションにおいては、効率的に発話するため「スマホ」などの略語に代表される新しい言葉が出現しやすい。
また、本来の意味とは異なる言葉の表現が瞬時に拡散され、定着することもあるだろう。
その結果、使われなくなった言葉は消滅に瀕するのだ。
加えて、このような社会においては、一部の地域でしか通じない方言より共通語を話す者が増え、方言の消滅の一因となる。
こうした言葉の変化は、どのような影響をもたらすか。
第一に、世代間の相互理解が困難になることだ。
従来からの言葉を用いる者と新しい言葉を用いる者とで、言葉の用い方が異なれば、コミュニケーションで齟齬や誤解を招く可能性がある。
第二に、地域の伝統や文化が継承されなくなることだ。
方言は地域で育まれてきた文化を表現するものである。
したがって、方言の担い手が減少すれば、文化の継承が断絶する懸念がある。
(2)
それでは、言葉についての関心を喚起し、理解を深めるために、国はどのような取組を行う必要があるか。
第一に、言葉について考える教育の機会を一層充実するべきである。
これまで、学校教育においては「正しい言葉」を理解するための学習が行われてきた。
しかし、情報化社会に身を置くにつれ、次第に本来の言葉の意味を忘れてしまう者は多いだろう。
したがって、「正しい言葉」に加えて、言葉の意味の変化や新しい言葉の出現に関して事前に理解しておくことが重要だ。
たとえば、「ら抜き言葉」などの表現をあえて教え、本来の表現やそれが変化したメカニズムを同時に学ぶのである。
こうした教育により、自らが用いる言葉を意識的に見つめ直すことができるようになるだろう。
普段は「ら抜き言葉」を使うことがあっても、目上の人と話す時や文章を書く時は本来の使い方ができるはずだ。
国は、このような教育を実施するための環境を整備し、先進的な事例を広く周知する役割が求められる。
第二に、地域文化に触れる機会を一層充実するべきである。
たとえば、地域の民話や伝統を披露するイベントに地域住民が慣れ親しんだり、学校教育において高齢者との交流を通して児童生徒が方言を学ぶことで、地域独自の言葉について関心や理解を深めることにつながるだろう。
現在は自治体で独自に行われることが多いこうした取り組みを、国として一層促進することが重要だ。
国は、地域の言葉に触れる取り組みを地域社会全体として進められるよう、フォーラムなどの機会を設け、学校や地域団体が連携できる環境を整える役割が求められよう。
言葉はコミュニケーションのツールであるとともに、地域の文化そのものでもある。
国は、上記の取組を通じて言葉の重要性を喚起しなければならない。
【国家一般職】論文模範解答例「2014年過去問:グローバル人材」
【国家一般職】論文テーマ
世界は、グローバル化が急速に進展し、人や物、情報等が国境を越えて行き交う大競争の中にあります。
日本が将来にわたって国際社会の中で信頼、尊敬され、存在感を発揮しつつ発展していくためには、多様な人材が、社会の様々な分野で活躍することが求められます。
また、少子・高齢化の進展に伴い、生産年齢人口が大幅に減少していく中で、経済成長を持続していくためには、イノベーションの創出を活性化させるとともに、人材の質を飛躍的に高めていく必要があります。
そのためには、教育の在り方が決定的に重要であり、若者の能力を最大限に伸ばしていくことが不可欠です。
(1)今日の社会の変化とその背景を述べ、それに対応するため、育成を図るべき能力について、あなたの考えを述べなさい。
(2)(1)で述べたような能力を培うために、初等中等教育においてどのような取組を行うべきかについて、具体例を挙げながら述べなさい。
【国家一般職】論文模範解答例
(1)
グローバル化が加速する今日の国際社会において、異なる文化との共存や国際協力の必要性が増大している。
加えて、少子高齢化が深刻化する我が国が、今後も国際社会で存在感を発揮しつつ発展していくためには、人材の質を飛躍的に高めなければならない。
グローバル化した国際社会において活躍できる人材として、育成を図るべき能力は何か。
それは、異なる価値を乗り越えて他者と対話し関係を構築するための「コミュニケーション力」と、異文化や社会問題に関心を持ち解決するための「創造力」であると考える。
(2)
上記の能力の育成を図るにあたり、課題はなにか。
第一に、国際社会で通用する高い語学力を培う必要があることだ。
他者と円滑にコミュニケーションを図るためには、自分の考えを正確に伝えられるとともに、相手の考えを深く理解できる語学力が欠かせない。
第二に、自ら課題を発見し解決する経験が求められることだ。
教師から一方的に知識を教授される従来の学習だけでは、創造力を養うのは難しい。
それでは、国はどのような取組を行う必要があるか。
第一に、海外で通用する実践的な英語力を修得できるよう、段階的に支援するべきである。
まず、小学校では英語に慣れ親しむことが重要だ。
そのために、英語の歌を歌ったり、英語でクイズを出すなど、児童が楽しんで学習できるよう工夫するとよいだろう。
次に、中学校では英語で日常会話ができる力を育んでいく。
日常の様々な場面や状況について、生徒が自分なりに英語で表現するロールプレイを積極的に取り入れたい。
そして、高校では英語を使って情報を理解し伝える能力を伸ばし、社会生活でも活用できることを目指す。
たとえば、英語のプレゼンテーションや討論を授業に取り入れるほか、海外勤務や留学経験のある社会人を非常勤講師として招き、実践的な英語を教わることが有効であろう。
第二に、自ら課題を発見し解決する能動的な学習の機会を提供し、創造力の向上を図るべきである。
社会で直面する課題は、唯一の正解が無い場合がほとんどであろう。
そのような問題に対峙しても、主体的に解決に導く能力を育む必要がある。
具体的には、アクティブラーニングの活用が有効と考えられる。
中学生や高校生の段階で自ら研究テーマを設定し、教師や外部人材に指導を仰ぎながら1年近くをかけてじっくりと調査研究を重ね、成果を論文にまとめた上で発表する。
こうした経験を通して、自ら考えて行動し、常に問題意識を持って課題解決に当たっていく姿勢が培われるだろう。
我が国の将来を担う人材の質を高める上で、教育は重要な意義を持つ。
我が国は、上記の取組を通じて国際社会で活躍する人材の育成に努めなければならない。