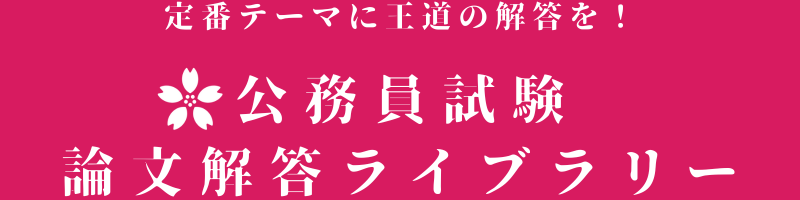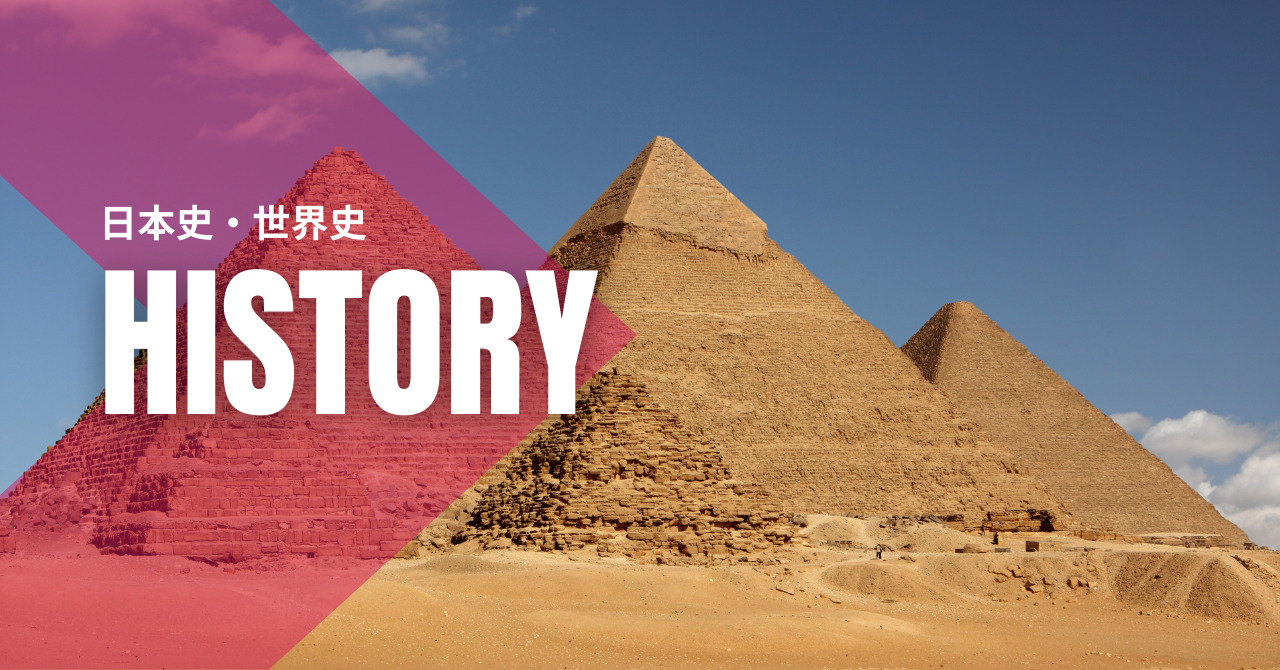こんにちは!編集長です。
編集長の専門は論文対策ですが、教養科目を教えることも大好きです。
そこで、今回は質問を受けることが多い「日本史・世界史」の勉強法をお伝えします。
ポイントをおさえると、おもしろいように問題が解けるようになりますよ。
ポイント①:時代ごとの大きな流れを理解する
日本史・世界史はたくさんの時代のできことを学ばないといけません。
1つずつ覚えるのは時間がかかるし、忘れてしまいやすくなります。
勉強の最大のコツは、細かな知識を暗記する前に、各時代の大まかなあらましを理解することです。
それを土台にして、細かなできごとや知識を肉付けしていきます。
たとえば、こんな感じです。
世界史の中世分野はこれをおさえれば十分です。
「意外とイケそうだな」と思いますよね。
ポイント②:できごとの因果関係を理解する
日本史・世界史の知識を覚えるコツはもう一つあります。
それは、できごとの因果関係、つまり「何が原因となったのか」「そこから何が生まれたのか」を理解することです。
できごとを1つずつ覚えるのではなく、いくつかを鎖のようにつなげて覚えます。
ポイント①と同じように、一度覚えると忘れにくくなります。
ポイント①はマクロ的な視点で、ポイント②はミクロ的な視点です。
たとえば、「十字軍の遠征」から「封建制の崩壊」までのできごとはこのとおり。
物語のようで、覚えやすそうですよね。
ポイント③:勉強の範囲を広げすぎない
日本史・世界史は、やろうと思えばいくらでも広く深く勉強できる学問です。
勉強がすすむと、細かい知識が気になって専門書籍やネットで調べたくなることがあります。
国家総合職を受験する場合や、過去問を解く上で必要な知識を調べるのであれば、問題ありません。
ですが、過去問にも出てこない情報を調べるのに時間をかけるのは、効率を大きく低下させてしまうので控えましょう。
公務員試験は、過去に問われた知識が問題文を変えて繰り返し問われます。
過去問を解いて基礎知識を習得した上で、余裕があれば応用知識を蓄えていきましょう。
日本史ノート
紹介したポイントをおさえた学習ができるように、「日本史ノート」をつくりました。
過去問演習をするときの「レジュメ」としてつかえるノートです。
ぜひ活用してみてください。
日本史ノートの特徴は、もちろんこのとおりです。
それではどうぞ。
1.原始時代
原始時代が出題されることは、あまり多くありません。
各時代の生活の様子を比較できるようにしておきましょう。
①旧石器時代
・大陸と地続き
・打製石器
・狩猟や採集生活
・土器なし
②縄文時代
・貝塚
・磨製石器
・狩猟や採集生活
・縄文土器
・貧富の差なし
③弥生時代
・高床倉庫
・青銅器や鉄器
・稲作
・弥生土器
・貧富の差あり
2.中央集権国家の確立
①大和政権
大和政権の根幹をなす氏姓制度や経済基盤、大陸とのまじわりを理解しましょう。
・氏姓制度
・私地私民制
・挑戦半島に進出
・古墳文化
・漢字、儒教、仏教の伝来
②聖徳太子の政治
初の女性天皇を補佐した聖徳太子の政治をおさえましょう。
・仏教の受容をめぐる豪族の争い
・冠位十二階の制
・憲法十七条
・遣隋使
・飛鳥文化
③律令国家の成立
大化の改新と律令国家の内容をチェックしましょう。
・大化の改新
・改新の詔「公地公民制、班田収受法」
・天智天皇「近江令」⇒天武天皇「八色の姓」
・大宝律令「二官八省、税制、中央集権の成立」
④奈良時代
藤原氏の政界進出、公地公民制の崩壊が大きな変化です。
・藤原不比等の政界進出
・仏教の鎮護国家思想(社会不安への対応)
・三世一身法、墾田永年私財法
・天平文化
3.平安時代
794年に都が平安京に移されてから、鎌倉幕府が開かれるまでの約400年間が平安時代です。
つぎの5つの流れをおさえましょう。
①律令制度の再建
・桓武天皇「平城京⇒永岡京⇒平安京へ遷都、勘解由使、健児の制、蝦夷征伐」
・嵯峨天皇「検非違使」
②摂関政治の確立
・藤原冬嗣「蔵人頭、藤原薬子の変」
・藤原良房「摂政」
・藤原基経「関白」
・藤原時平「菅原道真を左遷」
・醍醐天皇、村上天皇「延喜天暦の治」
・藤原道長、藤原頼道「摂関政治の全盛期」
③院政
・後三条天皇「荘園整理令により藤原氏の力を抑制」
・白河上皇「院政の開始」⇒鳥羽上皇⇒後白河上皇
④荘園の発達
・墾田地系荘園「貴族や大寺院の私有」
・寄進地系荘園「中央の権力者に寄進し、不輸権や不入権を獲得」
⑤武士の台頭
・承平天慶の乱「平将門、藤原純友」
・前九年後三年の役
・保元平治の乱「後白河天皇と崇徳上皇、平清盛と源義朝」
・平清盛「太政大臣、日宋貿易」
4.鎌倉幕府
鎌倉幕府の職制図、各執権の政策、崩壊までのながれが重要ポイントです。
①幕府の組織
・中央「侍所、公文所⇒政所、問注所」
・地方「守護、地頭」
②執権
・北条時政(初代)「執権の地位を確立」
・北条義時(2代)「承久の乱、六波羅探題の設置」
・北条泰時(3代)「御成敗式目の制定」
・北条時頼(5代)「皇族将軍の設置」
・北条時宗(8代)「元寇」
・北条貞時(9代)「得宗専制政治、永仁の徳政令」
③産業と土地支配
・農業「牛馬耕や二毛作が近畿、中国地方に広がる」
・経済「三斎市、借上、問丸」
・土地支配「地頭請、下地中分」
④建武の新政
・鎌倉幕府の滅亡「後醍醐天皇、足利尊氏らが倒幕」
・建武の新政の崩壊「後醍醐天皇が武士を冷遇したため、足利尊氏により崩壊」
・南北朝の対立「北朝の足利尊氏と光明天皇、南朝の後醍醐天皇」
・室町幕府の成立「建武式目、征夷大将軍」
・南北朝の合体「3代将軍足利義満の呼びかけに南朝が応じる」
5.室町幕府
南北朝の対立をのりこえたものの、守護が力をつけ、応仁の乱以降、下克上の機運がたかまり戦国時代に突入していきます。
①管制
・将軍補佐「三管領」
・中央「侍所、政所、問注所、評定衆」
・地方「鎌倉府、関東管領、守護、地頭」
②守護の権限拡大
・守護の権限「大犯三カ条、刈田狼藉、使節遵行、守護請、半済令」
・守護大名
③惣村と一揆
・惣村の発達
・土一揆「経済的要求」
・国人一揆「政治的要求」
・一向一揆「一向宗の門徒による一揆」
④戦国時代へ
・応仁の乱「幕府の権威失墜」
・戦国大名
・分国支配「分国法、貫高制」
⑤室町文化
・北山文化「足利義満、金閣、観阿弥世阿弥、五山十刹の制、五山文学」
・東山文化「足利義政、銀閣、雪舟、侘茶」
・狂言、連歌、御伽草子
⑥産業と土地支配
・農業「牛馬耕や二毛作が全国に広がる」
・経済「六斎市、土倉、酒屋、問屋、馬借」
・都市「門前町、城下町、寺町、港町、自治都市」
・土地支配「守護請、半済令」
6.織豊政権
ヨーロッパ人の来航、そして織田信長と豊臣秀吉による天下統一の流れと両者の政策をおさえましょう。
①ヨーロッパ人の来航
・鉄砲伝来「ポルトガル人」
・キリスト教伝来「イエズス会」
・天正遣欧使節団
・南蛮貿易、活版印刷技術
②織田信長の統一事業
・桶狭間の戦い⇒京都上洛⇒姉川の戦い⇒延暦寺焼打ち⇒室町幕府滅亡⇒長篠の戦い⇒本能寺の変
・指出検地
・楽市楽座
・仏教弾圧、キリスト教保護
③豊臣秀吉の天下統一
・山崎の戦い⇒大阪城築城⇒小牧長久手の戦い⇒関白就任⇒太政大臣就任⇒小田原攻め⇒奥州平定
・太閤検地「石高制、荘園制崩壊」
・刀狩令
・人掃令
・キリスト教禁止
・サンフェリペ号事件
・朝鮮出兵
④桃山文化
・障壁画「狩野永徳」
・茶道「千利休」
・阿国歌舞伎「出雲の阿国」
7.江戸時代
江戸時代は、仕組みを整える前期、失政と改革の中期、開国と倒幕の後期にわけて理解するのがおすすめ。
公務員試験において頻出の分野なので、集中して取りくみましょう。
①江戸幕府の仕組み
・幕府の成立「関ヶ原の戦い⇒幕府成立⇒大阪の役⇒大阪冬の陣⇒大阪夏の陣」
・幕府の組織「大老、老中、若年寄、寺社奉行、京都所司代、大阪城代」
・幕府の経済基盤「直轄天領400万石、旗本領300万石、鉱山、重要都市」
・大名統制「一国一城令、武家諸法度」
・朝廷公家統制「禁中並公家諸法度」
・寺院統制「諸宗寺院法度」
・農民統制「村方三役、本百姓、水呑百姓、慶安の御触書」
②外交と鎖国
・朱印船貿易
・ヨーロッパ諸国「リーフデ号漂着、平戸商館、慶長遣欧使節団、糸割符制度」
・アジア諸国「朝鮮通信使、謝恩使、慶賀使」
・鎖国「禁教令⇒ヨーロッパ船の来航を平戸と長崎に限定、イギリスが退去、日本船の海外渡航を禁止⇒島原の乱⇒ポルトガル船の来航を禁止⇒オランダ人を出島へ移送⇒鎖国完成」
③武断政治から文治政治へ
・武断政治の功罪「大名の処罰⇒牢人の発生⇒由井正雪の乱⇒文治政治への転換」
・5代将軍徳川綱吉の政治「湯島聖堂、生類憐みの令、質の低い元禄金銀の発行」
・新井白石の政治「6代と7代将軍を補佐、貨幣の改鋳」
④政治改革
・8代将軍徳川吉宗の政治「享保の改革、上げ米、足高の制、相対済し令、公事方御定書、目安箱、株仲間の公認」
・田沼意次の政治「10代将軍徳川家治の老中、株仲間の奨励、長崎貿易の奨励、貨幣制度の改善」
・松平定信の政治「11代将軍徳川家斉の老中、寛政の改革、囲米、七分積金、旧里帰農令、棄捐令」
・天保の大飢饉、大塩平八郎の乱
・水野忠邦の政治「12代将軍徳川家慶の老中、天保の改革、人返しの法、株仲間の解散、上知令」
⑤開国と不平等条約
・外国船の接近「ラクスマン、レザノフ来航⇒フェートン号事件⇒異国船打払令⇒モリソン号事件⇒アヘン戦争⇒薪水給付令」
・日米和親条約「開国、下田と函館開港」
・日米修好通商条約「関税自主権の欠如、領事裁判権の容認、神奈川、長崎、新潟、兵庫開港」
・不平等条約の影響「経済の混乱、安政の大獄⇒桜田門外の変」
⑥尊王攘夷運動と幕府の滅亡
・公武合体政策
・薩摩藩の対外問題「生麦事件⇒薩英戦争」
・長州藩の尊王攘夷運動「下関外国船砲撃事件⇒八月十八にちの政変⇒池田家事件⇒禁門の変⇒第1次長州征伐⇒四国連合艦隊下関砲撃事件」
・幕府の滅亡「第2次長州征伐⇒薩長同盟⇒15第将軍徳川慶喜就任⇒大政奉還⇒王政復古の大号令⇒戊辰戦争」
⑦文化
・元禄文化「上方中心の町人文化、井原西鶴、近松門左衛門、松尾芭蕉、尾形光琳、菱川師宣」
・江戸時代前期の学問「朱子学、陽明学、古学、和算」
・化政文化「十返舎一九、滝沢馬琴、小林一茶、東洲斎写楽、葛飾北斎、歌川広重」
・江戸時代後期の学問「国学、蘭学、伊能忠孝、平賀源内」
⑧産業と経済
・農業「備中鍬、千歯こき、油かす、商品作物」
・工業「農村家内工業⇒問屋制家内工業⇒工場制手工業」
・交通「五街道、菱垣廻船、樽廻船」
・経済「両替商、藩札、問屋商人」
8.明治時代
明治新政府の諸政策と、条約改正を経て日清・日露戦争にいたる流れをおさえましょう。
①明治維新
・五箇条の御誓文「天皇親政」
・五榜の掲示「民衆運動禁止」
・改元「明治」
・版籍奉還「領地と領民を天皇に返上」
・廃藩置県「国内の政治的統一」
・徴兵令「満20歳の青年男子に3年間の兵役」
・開拓使「北海道の開拓と防衛」
・国立銀行条例「渋沢栄一」
・地租改正「地価の3%⇒農民一揆⇒地価の2.5%」
・身分制度の廃止「華族、士族、平民」
・秩禄処分「武士出身者への支給打ち切り」
・廃刀令「武士の帯刀禁止」
・征韓論「不満を持った士族による主張」
・士族の反乱「西南戦争」
②明治初期の外交
・日清修好条規「外国と初めて結んだ対等な条約」
・日朝修好条規「朝鮮にとっての不平等条約」
・樺太千島交換条約「樺太はロシア、千島は日本」
③不平等条約の改正
・岩倉具視「条約改正の予備交渉、失敗」
・寺島宗則「失敗」
・井上馨「欧化政策、鹿鳴館、失敗」
・大隈重信「交渉中止」
・青木周蔵「大津事件、交渉中止」
・陸奥宗光「一部回復」
・小村寿太郎「完全回復」
④日清戦争と日露戦争
・日清戦争「甲午農民戦争⇒朝鮮が鎮圧を清に依頼⇒日本出兵⇒日清戦争屋→日本勝利」
・下関条約「朝鮮の完全独立、リャオトン半島割譲、賠償金2億両」
・三国干渉「ドイツ、フランス、ロシア」
・義和団事件「ロシアの満州占領」
・日英同盟「ロシアに対抗」
・日露戦争「満州、朝鮮問題の交渉が決裂し、開戦」
・ポーツマス条約「米ルーズベルト大統領の斡旋、賠償金なし⇒日比谷焼打ち事件」
・韓国併合「統監府⇒伊藤博文暗殺⇒韓国併合⇒朝鮮総督府」
⑤産業革命と社会主義運動
・第一次産業革命「日清戦争前後、軽工業」
・第二次産業革命「日露戦争前後、重工業」
・社会主義運動「資本主義の発展⇒大逆事件、治安警察法、工場法」
⑥文化
・思想「福沢諭吉、明六社、天賦人権思想」
・教育「文部省設置⇒学制⇒教育令⇒学校令⇒教育勅語発布」
・宗教「神仏分離令、キリスト教解禁」
・外国人「クラーク、フェノロサ、ボアソナード」
9.大正~昭和初期
大正は護憲運動からはじまり第一次世界大戦が勃発するながれを、昭和初期は経済不況から脱却するために大陸へ進出し第二次世界大戦へむかうながれを中心に整理しましょう。
①護憲運動
・第一次護憲運動「桂園時代⇒国民の不満⇒大正天皇即位⇒第一次護憲運動」
・第一次山本権兵衛内閣「シーメンス事件」
・第二次大隈重信内閣「第一次世界大戦、21カ条の要求」
・寺内正毅内閣「シベリア出兵、米騒動」
・原敬内閣「初の政党内閣、普通選挙法は消極的」
・第二次護憲運動「清浦奎吾内閣⇒第二次護憲運動⇒加藤高明内閣、普通選挙法、治安維持法」
②第一次世界大戦
・開戦「日英同盟によりドイツへ宣戦布告⇒21カ条の要求⇒ドイツ権益引き継ぎ」
・ロシア革命「シベリア出兵⇒米騒動⇒寺内正毅内閣総辞職⇒原敬内閣」
・パリ講和会議「ベルサイユ条約」
・アジアの民族運動「五四運動、三一運動」
・国際連盟設立「米ウィルソン大統領の提案」
③金融恐慌
・大戦景気「大戦中は好景気⇒大戦後は反動で不景気」
・金融恐慌「関東大震災⇒銀行の経営悪化⇒金融恐慌⇒田中義一内閣がモラトリアム⇒金融恐慌終結」
・昭和恐慌「浜口雄幸内閣が金解禁⇒アメリカの世界恐慌⇒昭和恐慌⇒大陸進出へ」
④第二次世界大戦
・張作霖爆殺事件「辛亥革命⇒孫文⇒蒋介石の北伐⇒山東出兵⇒張作霖爆殺⇒田中義一内閣退陣」
・満州事変「柳条湖事件⇒第二次若槻内閣総辞職⇒犬養毅内閣⇒上海事変⇒満州国建国⇒五・一五事件⇒国際連盟脱退⇒二・二六事件」
・日中戦争「盧溝橋事件⇒日中戦争⇒抗日民族統一戦線⇒国家総動員法」
・第二次世界大戦「ドイツとソ連の不可侵条約⇒ドイツのポーランド侵攻⇒イギリス・フランスの宣戦布告⇒第二次世界大戦」
・日独伊三国同盟「第二次近衛内閣」
・太平洋戦争「日ソ中立条約⇒ABCD包囲陣⇒東条英機内閣⇒真珠湾攻撃」
・終戦「ミッドウェー海戦⇒本土空襲⇒ドイツ降伏⇒原爆投下⇒ソ連の参戦⇒ポツダム宣言受諾」
10.戦後の歩み
GHQによる占領下での改革や、おもな内閣とできことを結びつけておぼえましょう。
①GHQによる間接統治
・治安維持法と特高警察の廃止
・財閥解体
・婦人参政権「満20歳以上の男女」
・労働改革「労働組合法、労働関係調整法、労働基準法」
・天皇の人間宣言
・農地改革「第一次農地改革⇒第二次農地改革⇒自作農創出」
・東京裁判
・日本国憲法の制定「GHQの改正案⇒幣原内閣の原案⇒日本国憲法施行」
・教育改革「教育基本法、教育委員会」
・傾斜生産方式「石炭業、鉄鋼業、復金インフレ」
②冷戦
・冷戦の開始
・中華人民共和国の成立
・経済安定九原則「ドッジライン、予算の均衡、徴税強化、賃金安定、物価統制」
・シャウプ勧告「税制改革」
・朝鮮戦争「日本に警察予備隊⇒保安隊⇒自衛隊」
・国際社会への復帰「サンフランシスコ平和条約、国連加盟はなし」
③高度経済成長期
・鳩山一郎内閣「55年体制、日ソ共同宣言」
・岸信介内閣「新安保条約⇒抗議運動⇒総辞職」
・池田勇人内閣「所得倍増計画、政経分離」
・佐藤栄作内閣「日韓基本条約、沖縄返還」
④自民党長期政権と崩壊
・田中角栄内閣「日中共同声明、列島改造論」
・高度経済成長の終わり「第一次石油危機、ロッキード事件」
・福田赳夫内閣「日中平和友好条約」
・中曽根康弘内閣「3公社民営化」
・プラザ合意「ドル高是正⇒円高」
・バブル経済「超低金利政策⇒地価や株価の高騰」
・55年体制の崩壊「自民党過半数割れ⇒細川内閣」
・橋本龍太郎内閣「日米安保共同宣言、ガイドライン見直し」
・バブルの崩壊
⑤近年の政権
・小泉純一郎内閣「聖域なき構造改革、テロ対策特別措置法、郵政民営化」
・民主党へ政権交代
・安倍晋三内閣「アベノミクス3本の矢、日米同盟の強化、国家安全保障会議、特定秘密保護法、憲法改正」